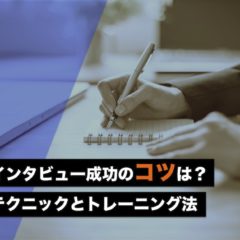記事外注でおすすめの会社10選【同業者が厳選】|依頼のコツも解説
( 最終更新日:2023年5月16日)
記事作成の外注を検討されている企業のWeb担当者の方々に向けて、記事作成会社である弊社YOSCAが、同業者としておすすめできる、信頼できる、良い噂を聞く10個の記事作成代行サービスの解説と、求める記事を制作してもらうための依頼のコツをご紹介します。
当記事を用意するにいたった背景には、記事外注に失敗してしまい、弊社へご相談いただく担当者様が少なくないためです。詳しくお話を伺うと、制作会社選びに失敗していたり、外注する前の準備が足りず記事作成会社と連携が取れなかったりという理由がほとんどです。
記事作成の外注は本来、Web担当者がこれまで記事制作に充てていた時間を、自分にしかできない他の作業に充てることができたり、プロに依頼することで質の高い記事を用意できたりするメリットがあります。
記事外注に失敗し、自身で書き直すなどの手間が余計にかかるなど、上記のメリットを享受できないまま記事の外注を諦めてしまうような事態はとても不幸なことです。当記事を通して、Web担当者の方々が当たり前に記事の外注に成功し、ビジネスで成果を残すことにつながればと思います。ぜひご覧ください。
目次
記事の外注で失敗する3つのパターン
まず、記事の外注に失敗したお客様からお聞きした事例を元に、記事外注に失敗するパターンを3つ紹介します。
- 制作料金の安さだけで決めてしまった
- 相手に任せすぎてしまった
- 記事作成の目的を明確にしていなかった
制作料金の安さだけで決めてしまった
記事を外注するにあたって、当然費用はかかってきます。依頼する側としては、安く済むに越したことはありません。予算がある程度決まっているなかでやりくりする必要があったり、自身で決済判断できる金額が決まっていたりなど、予算面で苦労している担当者の方々も多くいらっしゃいます。
記事の制作において、決して「安かろう悪かろう」ということはありません。安くても求める記事を納品してもらうことは可能です。
ただし、文字単価の料金だけを比較して制作会社を決めてしまったばかりに、「てにをは」の間違いや記事のトーンがばらばらの記事や、意図していない内容が書かれた記事が納品されてしまうケースがあります。また、低単価のサービスでは、記事の修正対応を受け付けていない場合がほとんどです。結果的に、担当者自身で書き直す手間が発生してしまうことになります。
安いにはそれなりの理由があります。制作料金だけではなく、サービス内容をしっかりと把握しなければなりません。
相手に任せすぎてしまった
記事の制作において、「高かろう良かろう」ということもありません。「記事制作会社のサービスページを見て、実績がすごいから任せておけば大丈夫だと思ってしまった」「単価が高いライターなので、信頼できるだろうと思って安心してしまった」というお声を聞きます。
たしかに実績は制作会社選びの参考になりますし、単価が高いライターは経験値が豊富で良い記事を執筆してくれます。しかし、記事の作成は依頼主と書き手の共同作業。記事の完成イメージを相互にすり合わせる時間が必要です。記事ができあがってから、「イメージと違った」となっては、修正を依頼する手間がかかってしまいます。また、事前に聞いていない内容のため修正対応を受け付けられないといったトラブルに発展することもあります。
記事作成の目的を明確にしていなかった
「とりあえず外注して自分の時間を確保したい」「とりあえず記事数を増やしてPVを増やしたい」「とりあえず自社ブログを更新したい」といった漠然とした目的での外注では、記事作成の成果は出づらいです。
何の目的のためにメディアを運営していて、記事数を増やす必要があるのか。また、どんな記事を作って、どんな読者に読んでもらいたいのか。こういった制作意図を明確にしないまま記事の制作を外注してしまうと、不要なテーマの記事が作成されてしまったり、狙っていない読者層にリーチする記事ができあがってしまったり、競合度合いが高いテーマでばかり記事を作ってしまいアクセスがまったく伸びなかったりなど、余計なコストがかかってしまいます。
記事の外注で失敗しないために準備・注意しておきたいこと
外注の失敗を避けるためには、発注前の準備が大切です。以下のポイントを押さえておけば、記事外注で大きな失敗をすることはないでしょう。
依頼の目的を明確にする
1つ目のポイントは「依頼の目的を明確にする」」ことです。
具体的には、
- 新規顧客獲得につなげるために、Webサイトへ見込み客の流入を増やしたい。
- 商品やサービスの販売促進、コンバージョン率のアップを図りたい。
- 企業のブランディング活動として、情報を広めたい。
などです。
各企業によってメディアを運営する目的は様々です。どんな目的を達成するために記事作成を行うのか、記事を作成して、どんな現象を起こしたいのか、をはっきりさせましょう。目的が明確になることで、どんな記事を作成する必要があるのかも決まります。
本当に外注する必要があるのか考える
これは、記事作成をそもそも外注する必要があるのか、外注する意味があるのかを考えるということです。
記事外注のメリットは、先述の通り、業務効率面とクオリティ面にあります。
例えば、自社がニッチな分野のエキスパートで、記事を作成する目的が自社のブランディングだった場合、単に外注したとしても、期待以上の内容の記事があがってくることは少ないでしょう。ライターから自身がインタビューを受けたり、あがってきた原稿を細かく修正したりする可能性は大いに考えられます。修正する前提で、たたき台を作ってもらうことが目的であれば、業務効率面でのメリットはあるかもしれません。ただし、自身でイチから執筆するよりも、かえって手間がかかってしまうこともあるでしょう。それぞれを天秤にかけて、外注を判断する必要があります。
その他、記事作成の目的は新規顧客獲得だが、早期に成果を上げなければいけないといった企業の場合、記事作成外注は向いていないかもしれません。分野が競合ひしめくジャンルであればなおさらです。記事作成、メディア運営による営業成果は年単位で見なければならない場合があります。
このように、依頼の目的を達成するために、本当に記事外注が適しているのかを考えてみましょう。もし判断がつかなければ、記事制作会社に相談してみることをおすすめします。そこでの対応や返答内容によって、その制作会社が信頼できるかの判断材料にもなります。
予算を確保できているか
記事外注にかけられる費用が予算内に収まるのかを事前に考えます。
かかる費用を算出するためには、目的を達成するための大まかな計画が必要です。具体的には、どれくらいの期間で、何本の記事を作成する必要があるのかを考えます。そして、予算を制作予定本数で割ることで、1記事あたりの外注にかけられる費用が算出できます。
もし希望するサービスを利用する場合の外注費用が予算に収まらないのであれば、予算を増やしてもらう、予算内で収まるサービスを選択する、外注する記事本数を減らす、外注する業務を削る、計画を変更するなど総合的に考えて意思決定する必要があります。
このとき、計画を無理やり遂行するために、安易に記事単価の安いサービスを選択しないよう気をつけてください。成果が出なければ、外注費用がすべて無駄になってしまいます。予算内で最大限に成果が出る方法を考えましょう。
外注したい業務内容は決まっているか
どこまでの範囲を外注したいのか、事前に考えておきましょう。
例えば、Web集客を目的とした記事作成には、一般的に以下の業務があります。
記事作成の流れ
|
上記を外注業務に分類すると、
- 記事の執筆
- 画像の用意
- 記事の投稿
- 対策キーワードの選定
- 記事の企画
- 文章構成の作成
になります。
外注先のサービス対応範囲にもよりますが、どこまでを外注したいのか、何を外注することで業務効率が上がるのかを考えておきましょう。
記事の外注先を選ぶ際のポイント
続いて、事前に考えておいたことを元に、記事の外注先を選んでいきます。外注先はライター個人と、記事作成会社に分かれます。それぞれの場合でのメリット、デメリットと、選ぶポイントについて紹介します。
記事作成会社に発注するメリット、デメリット
記事作成会社の強みは、多数の記事をスピーディかつ安定したクオリティで制作できる体制があることや、SEO対策に対する実績やノウハウを持っていることです。また、ライターの手配や納品管理、記事の細かなチェックなどの制作工程の手間をすべて請け負ってくれるところもメリットといえます。
一方で、製作工程を請け負ってくれる分、ライター個人に依頼するよりは外注費用がかさみます。また、専門性の高い記事の制作となると、一般的な記事よりも高単価になり、割高に感じてしまう場合もあるかもしれません。
(参考)記事外注費用の相場(文字単価換算)
・記事作成会社:1文字3〜10円
・クラウドソーシング/ライター個人:1文字1〜3円
記事作成会社を選ぶポイント
ヒアリング・提案を丁寧にしてくれるか
要件を細かくヒアリングしてくれる会社は面倒と思われるかもしれませんが、むしろ丁寧な会社と考えましょう。ヒアリングが足りないばかりに、原稿を納品したあとにイメージと違ったとなる会社は少なくありません。
さらに、「こうした記事を作成したい」「こうしたメディアにしたい」といった要望に対して、「それならこういったやり方で記事を作れる」「これならよりコストを抑えて、かつ効果の期待できる記事を用意できる」といった提案があるかどうかも見たいところです。
修正対応してくれるか
記事作成には、絶対の正解は存在しません。発注側を含めて読み手の好みも多分に入るため、納品した記事の修正は、その範囲や頻度、内容を巡ってトラブルになりやすい項目です。低単価の記事作成代行サービスの場合、修正対応をまったく受け付けていないところは多いです。修正についての規定を定め、わかりやすく提示している企業は信頼のおける会社といえるでしょう。
また、初回の発注では、記事の完成イメージのすり合わせ作業が大切です。オーダー時には伝えきれなかったニュアンスや表現の好み、言葉遣いなどを、執筆と修正を何度か繰り返しながら理想の記事を作りあげていくのです。こうしたすり合わせ作業に積極的に取り組み、かつ、修正における無償範囲と追加費用がかかる範囲をきちんと明示している会社を選びましょう。
作業範囲と料金体系は明確か
記事作成には多数の工程があることは先述した通りです。キーワード選定、構成案の作成、執筆などについてどこを発注側が行い、どこを請け負ってくれるのかを明確にしてくれる会社であれば、ライティングに必要な工程を理解しているとわかります。
また、依頼内容に応じた料金設定を提示してくれる会社を選びましょう。ライティング業界は相場がまちまちだからこそ、お見積もりを項目ごとに細かく出してくれる会社、しっかりとした基準に基づき丁寧にかつ明瞭に提示してくれる会社は信頼できます。
編集体制は整っているか
ライターが書いた記事を記事作成会社内の担当編集者がチェックし、納品される体制をとっている会社であれば、記事の質は保たれます。外注によって手間や時間を削減するためには、編集体制が整っている制作会社を選ぶことが重要です。また、最近では、コピーコンテンツかどうかのチェックをツールで行っている企業がほとんどですが、確認しておくといいでしょう。
実績を提示してもらえるか
その会社が過去にどのような記事を納品してきたのかは、企業選びで参考になります。可能であれば、自分たちの発注したい記事に近いジャンルでの実績を聞いてみましょう。もちろん守秘義務によって実績として提示できない例もあるでしょうが、依頼の参考として一度聞いてみましょう。
発注したいジャンルを得意としているか
発注したい記事ジャンルに専門的な知識を有したライターがいるのか、記事作成会社はどの分野を得意としているのか、を確認するとよいでしょう。詳しいから良い記事が書けるわけではありませんが、得意としている分、実績が多く、依頼する判断材料の一つになります。
テストライティング、または、少ない本数での発注は可能か
記事の仕上がりの程度を事前に知りたい場合は、テストライティング(無料、または割安に1記事制作してくれること)や、少ない本数での発注が可能か確認してみましょう。外注先としてもいきなり10 本、20本という数を引き受け、いっぺんに納品するのはトラブルのリスクがありますから、検討してくれることでしょう。双方のリスクを低くするために有効な方法です。ただし、テストライティングといえども費用がかかる場合がほとんどです。
ライター個人に発注するメリット、デメリット
ライター個人に発注する方法は、直接声をかける場合と、クラウドソーシングサービスを利用する2通りあります。いずれの場合においても、記事作成会社よりは安価に発注できることが多いです。また、クラウドソーシングを利用すれば、一度に大量の記事を外注することも可能です。
一方で、ライターを探す手間や、記事をチェックする手間がかかってきます。特に、安心して依頼できるライターを見つけるには時間がかかります。運良く見つかったとしても、関係性構築にも時間がかかるため、発注側にはライターとの円滑なコミュニケーションスキルが求められます。制作マニュアルを用意するなどの配慮も必要でしょう。
また、複数人に記事作成を発注した場合、記事の品質にバラつきがでやすいデメリットもあります。最悪の場合、他の記事をそのまま盗用(コピペ)したものや、別の依頼で書いた内容を使いまわした記事を納品されることも起こりえます。うまく活用しないと、大きな手間や、外注費用が無駄になってしまうこともあるでしょう。
ライターを選ぶポイント
プロフィールや実績、職務経歴などの情報がしっかりしているか
面識のない個人に仕事を依頼することは、企業にとって一抹の不安があります。優秀なフリーライターは、それを理解して、自身の信頼の証として、プロフィール情報や、これまでに執筆してきた記事の詳細な実績、単価などの情報を開示しています。
ライターは、記事を通して読者が必要としている情報を提供することが仕事です。プロフィール情報を通して発注主が必要としている情報を提供できていないライターは、記事の作成においても不安が残ります。
テストライティングは可能か
どんなに記事の実績が優れていたとしても、それがライターの実力とは言い切れないことがあります。できあがった原稿は、何度も編集担当が修正してできあがったものかもしれないのです。そのため、できることならテストライティング、もしくは一本のみの記事作成を受けてくれるライターが望ましいです。
円滑にコミュニケーションできるか
記事外注は、制作過程で細かなやり取りが発生するものです。そのやり取りにおいて、うまくライターと連携が取れなかったという方は多くいらっしゃいます。
そのため、社会人として基本的なコミュニケーションスキルをきちんと持ったライターを選ぶようにしましょう。見分けるポイントとしては、正しいビジネスメールの形式でやり取りできているか、丁寧な誤字脱字のない文章を送ってきているか、返信は早いかです。
記事外注におすすめの会社10選
上記を踏まえ、安心して記事外注できるサービス、企業を10社紹介いたします。お問い合わせ先のURLを掲載しているので、気になったところに問い合わせしてみて、外注先を比較、選定いただければと思います。
※掲載している情報は2021年12月時点の情報です。
記事制作代行│株式会社grooo
Webシステム開発や広告運用、旅行業WEB販売管理システムの運営など様々なサービスを提供する株式会社grooo(グロー)。記事作成代行サービスも提供していて、SEO対策用のコンテンツ制作に強みを持ち、記事の企画、設計、執筆までワンストップで対応しています。
特に強みとして挙げられるのが、キーワード分析です。漠然とPV数を増やすためのキーワードではなく、メディアの目的に即した本当に狙うべきキーワードをリサーチ、提案してくれます。
対応できる記事形式は、取材記事や医療や法律などの専門家が記事チェックを行う監修記事、体験談をベースとしたレビュー記事、まとめ記事、紹介記事、コラムと多岐にわたります。
プランが3つあり、定期的なコンサルティングなメディア運営のサポートからお願いしたい企業から、記事作成だけを希望の企業まで、幅広く対応しています。
- キーワード分析に強み
- 取材記事からコラム
- レビュー記事まで幅広く制作、コンサルティングプランもあり
| 運営企業 | 株式会社grooo |
| サービスプラン、料金目安 | ・記事作成プラン(記事構成/制作校正):記事作成費のみ ・ワンストッププラン(記事作成のほか、キーワード選定など):初期費用+記事作成費 ・コンサル運用プラン(戦略立案や効果測定レポート、月1の編集会議までフルサポート):初期費用+記事作成費) ※料金の確認は要お問い合わせ |
| 備考 | ご依頼は10本より対応。 |
| お問い合わせ | https://www.grooo.co.jp/contact/ |
| 本社 | 東京都新宿区西新宿8-1-2 PMO西新宿 3F |
WeiVライティング│株式会社NEXER
記事作成やサイト運営などのお役立ち情報を発信するWEBマガジン「WeiV(ウェイブ)」を運営する株式会社NEXER(ネクサー)の提供する記事作成サービスがWeiVライティングです。
SEOに強く集客できるWebコンテンツの制作を目的としたサービスで、これまで790社への提供実績があるサービスです。
これまで多くのクライアントのメディアサイトを制作し、また、自社でも多様なジャンルの
メディアを運営してきた経験があり、サテライトサイト用に作成されるような、ただキーワードが盛り込まてた記事ではなく、読者の感情を動かす記事の制作に取り組まれています。
業界相場としては、比較的安価な文字単価3円〜となっています。精緻なお見積は担当プランナーの方からヒアリングを受けてからとなります。
- メディアの制作、運営実績が豊富
- Weivを運営するNEXERではSEOコンサルティングサービスを10,000社以上に提供
- 比較的安価なミニマム文字単価
| 運営企業 | 株式会社NEXER |
| サービスプラン、料金目安 | ・ベーシックプラン(企画、タイトル、見出し作成、ライティング):1文字3円〜 ・シンプルプラン(ライティングのみ):1文字2円〜 |
| 備考 | 最低発注金額は10,000円。 納期目安:文字数やジャンルによって異なる。 |
| お問い合わせ | https://nexer.co.jp/weiv/lp/writting/ |
| 本社 | 東京都豊島区池袋2-43-1 池袋青柳ビル6階 |
コンテンツ制作│有限会社ノオト
有限会社ノオトでは、人のハートを動かすようなコンテンツをつくる会社と掲げている通り、丁寧な企画、取材、執筆、編集で質の高いコンテンツを制作します。クライアントの要望に合わせ、Web、紙媒体にも対応しています。
企画提案から、サイト設計(ワイヤーフレームの作成)、記事デザインなど、原稿作成の他にもじっくりと工数をかけてコンテンツを制作するため、比較的制作費用は高めです。しかし、読者に大きな反響を起こすような記事作成においては、非常に信頼度が高く、大手企業からの依頼実績は豊富です。 また、コンテンツ制作のほか、Twitter、Facebook、Instagramなどのソーシャルメディアの運営代行も行っています。
- オウンドメディアの立ち上げや運営から、コンテンツ作成まで対応
- 高価格な分、丁寧に工数をかけた質の高い記事を制作
- ソーシャルメディアの運営代行も対応
| 運営企業 | 有限会社ノオト |
| サービスプラン、料金目安 | 例)自社メディア用に4000字の記事を10本制作。 ・原稿制作(10本): 1,000,000円 ・編集費(10本):500,000円 ・画像手配(10本):50,000円 ・全体ディレクション・進行管理:200,000円 |
| 備考 | 記事1本のボリュームやサイトの運営方針などによって、最終的な制作費や運営費は異なる。 |
| お問い合わせ | https://www.note.fm/contact/ |
| 本社 | 東京都品川区西五反田1-13-7マルキビル5F |
コンテンツ制作│株式会社PLAN-B
SEOやネット広告などのデジタルマーケティング事業や、サイト制作などのメディア事業を提供している株式会社PLAN-B。SEO対策として、コンサルティングサービスとコンテンツ制作、「SEARCH WRITE」というSEO対策ツールの3つを提供しています。
コンテンツ制作では、コンテンツの企画設計、編集機能を備えた高品質なライティング、そして、コンテンツを多くのターゲットに届けるための流通施策(キーワード選定、SNSや広告配信など)までを手掛けてくれます。
ライターは、原則としてクラウドソーシングサービスは利用せず、自社で雇用しているライターや、付き合いのある外部ライターと連携して制作体制を築いています。
- 自社でSEO対策ツールを開発
- コンテンツの広告配信やSNSによる拡散にも対応可能
- SEOコンサルは別途月額30万円にて対応
| 運営企業 | 株式会社PLAN-B |
| サービスプラン、料金目安 | ・記事コンテンツ制作(企画設計、ライティング、流入施策、PDCA) 初期費用:30,000円〜 通常記事費用:30,000円〜 専門家記事費用:50,000円〜 ・記事型LP制作:100,000円〜 ・SEOコンサルティング:月額300,000円〜 |
| 備考 | 記事の修正は原則2回まで。 サイト制作、CMS入稿なども可能。 |
| お問い合わせ | https://service.plan-b.co.jp/contact/ |
| 本社 | 東京都品川区東五反田2-5-9 島津山PREX 3階 |
記事作成代行Pro│株式会社BRIDGEA
株式会社BRIDGEA(ブリジア)の提供する記事作成代行Proサービスは、5つのプランが特徴です。
顧客ニーズに合わせて、
- シンプルプラン(サテライトサイト用記事で目視・最終校正なし)
- ブロンズプラン(ディレクター、校正者によるダブルチェック)
- シルバープラン(アクセス数調査やキーワード選定込み)
- ゴールドプラン(サイト分析、既存コンテンツのりライトにも対応)
- プラチナプラン(サイト運営のパートナーとして、記事作成、画像挿入・入稿作業まで全てを対応。)
が用意されています。
オプションとして、WordPressへの入稿作業から、記事への画像挿入、SEOコンサルなどを用意していて、使い勝手の良いサービス体系となっています。
制作体制は、ライター・ディレクター・校閲者の3名体制(ブロンズプランから)。専任のライターがつくことで、クオリティコントロールできるところが強みです。また、新規の方に限り、テストライティングが50%OFFの特典があります。
- ニーズに合わせた5つのプランを用意
- 費用は文字単価3.5円〜7.5円
- インタビュー記事や、商品モニター記事、専門家監修記事の制作も可能
| 運営企業 | 株式会社BRIDGEA |
| サービスプラン、料金目安 | ・シンプルプラン:3.5円/文字 ・ブロンズプラン:4.5円/文字 ・シルバープラン:5.5円/文字 ・ゴールドプラン:6.5円/文字 ・プラチナプラン:7.5円/文字 |
| オプション | WordPress入稿:1.5円/1文字 画像挿入:800円/1枚 画像文字挿入:1,200円/1枚 SEOコンサル:100,000円/月額 |
| 備考 | 修正対応:当初の要望にない内容、修正依頼には対応できない。 納期目安:約1ヶ月 |
| お問い合わせ | https://article-pro.com/contact/ |
| 本社 | 長崎県西海市大島町4563-1 |
Web/取材ライティング│株式会社YOSCA
株式会社YOSCA(ヨスカ)は、SEOライティングから、コーポレートサイトのリニューアル、ブログ記事の制作代行、社内報、インタビューコンテンツ、音源の字幕作成など、テキストコンテンツ全般に対応する制作会社です。
「フリーライターのよりどころ」というライター向けのプラットフォームサービスを運営していて、約7,000名のライターが登録しています。また、ライタースクールを運営するなど、ライターの育成に力を入れているところが特徴です。制作体制は、編集者とライターのチーム制。案件に固定したライターをつけることが可能です。
YOSCAは、固定のオフィスを持たず、また、ライター、編集者とはすべて業務委託のパートナー関係、集客に広告費はかけず全てWeb集客など、できるだけ固定費や営業費用を落とした運営をしています。その分、相場よりも割安にサービスを提供しています。一方で、ライター、編集者への報酬割合が業界平均よりも高く、優秀なライター、編集者陣が長く在籍しています。
(参考)2015年『入門 SEOに効くWebライティング(出版:SBクリエイティブ)』を上梓。
- SEOからインタビュー、字幕作成など幅広い制作実績
- ライターの育成に注力している
- 業界相場よりも割安に高品質な記事を制作
| 運営企業 | 株式会社YOSCA |
| サービスプラン、料金目安 | ・Webライティング:文字単価5円〜 ・取材ライティング:記事単価40,000円〜 |
| オプション | 画像選定:1枚500円〜 イラスト(挿絵)制作作成:10,000円〜 構成案作成:1本あたり7,000円〜 専門家による記事の監修:10,000円〜 キーワード選定:要お問い合わせ |
| 備考 | 1本から記事作成対応 編集体制:健康や医療に関する専門編集チームが在籍 納期目安:初回打ち合せより3~4週間前後 |
| お問い合わせ | https://yosca.jp/contact.html |
| 本社 | 東京都渋谷区渋谷2-14-6 西田ビル5F |
コンテンツマーケティング│株式会社リファイド
株式会社リファイドが提供するサービスは、ニュース型記事とコラム型記事の制作です。特にニュース型記事とコラム型記事を組み合わせたハイブリッドコンテンツマーケティングプランでは、サイトへ安定したトラフィックをもたらすことが可能です。
専門的な分野を含め、多様なジャンルのコンテンツ制作が可能で、海外コンテンツにも対応しています。また、自社で開発した記事管理システムにより、自動で記事が更新される仕組みを用意。納品された記事をわざわざコピペして更新する手間が省けます。 また、満足度保証がついていて、無制限で修正に対応してくれるところも特徴的です。仮に記事に満足できなかった場合でも、契約の本数にはカウントされません。
- ニュース型記事とコラム型記事の制作プラン
- 自動更新機能の提供
- ユニークな満足度保証制度
| 運営企業 | 株式会社リファイド |
| サービスプラン、料金目安 | ・ニュース型記事コンテンツプラン 制作本数:月30本〜 文字数:1記事500〜700文字 画像:1枚〜 契約期間:基本12ヶ月 ・コラム型記事コンテンツプラン 制作本数:月5本〜 文字数:1記事1000〜1500文字 画像:1〜5枚 契約期間:基本12ヶ月 ・ハイブリッドコンテンツマーケティングプラン 上記2つのプランを組み合わせてカスタマイズ。 ※記事単価は数千円〜数万円の範囲。詳細な費用は要お問い合わせ。 |
| 備考 | サンプル記事を無償で制作。 準備期間として3〜4週間、約1ヶ月で納品開始。 |
| お問い合わせ | https://www.grooo.co.jp/contact/ |
| 本社 | 東京都新宿区西新宿8-1-2 PMO西新宿 3F |
コンテンツ制作代行│株式会社ルーシー
Webマーケティング、コンテンツマーケティングに関するお役立ちコンテンツの発信で有名な「バズ部」を運営する株式会社ルーシーのコンテンツ制作代行サービスです。「真に良質なコンテンツ」を提供することを理念に、バズ部公認ライターとバズ部スタッフが共同でコンテンツを制作します。
特徴は、バズ部独自のノウハウに基づいた「バズ部式ライティング」です。バズ部の運営と累計200社以上のメディア構築支援からくる実績とノウハウを基に、Googleが高評価するコンテンツを提供しています。
また、コンテンツは集客装置としての機能だけではなく、企業のブランドを強化することを意識して作っていることも特徴の一つです。サービス価格は比較的高価ですが、実績と提供する記事品質から鑑みれば納得です。
お問い合わせした方には「バズ部式マーケティング 広告費を1/10にして売上を倍増させる全手法」の資料を無料で入手できるので、お問い合わせの参考になさってみてください。
- バズ部のコンテンツ制作代行サービス
- 「バズ部式ライティング」による記事制作
- コンテンツマーケティングに関する資料を無料進呈
| 運営企業 | 株式会社ルーシー |
| サービスプラン、料金目安 | (参考)ホームページ制作プラン
スタンダードプラン:初期費用50万円、月額3万円 アドバンスプラン:初期費用100万円~、月額8万円 ※詳細は要お問い合わせ |
| オプション | キーワードリサーチ:別途費用 薬事(医師)チェック:なし |
| 備考 | ご依頼は10本より対応。 |
| お問い合わせ | https://bazubu.com/writing-lp |
| 本社 | 東京都港区西新橋2-7-4 CJビル11階 |
サグーワークス│株式会社ウィルゲート
サグーワークスは、Webコンサルティング事業とメディア事業を手掛ける株式会社ウィルゲートが運営するライティング案件特化型のクラウドソーシングサービスです。あまり予算をかけずに記事を外注したい方には使い勝手の良いサービスと言えます。
従来のクラウドソーシングサービスと違い、サグーワークス内のディレクターがライターの手配を行ったり、原稿のコピーチェックや、レギュレーション違反がないかの目視チェックなど記事のクオリティコントロールをしてくれたりします。そのため、ライターとのやり取りの手間がある程度省けるメリットがあります。
記事制作プランは、オンライン発注プランとオーダーメイドプランの2種類あります。オンライン発注プランでは、自身で対策したいキーワードや見出しなどの文章構成、画像の有無などを指定して依頼します。記事の執筆〜納品まではすべてオンラインで完結する手軽さがあります。
オーダーメイドプランでは、SEOコンテンツディレクターがキーワード選定、記事の企画などの相談に乗ってくれるプランです。専門家によるコラム記事や取材記事の作成も対応可能です。
また、各プランとも依頼できるライターが3種類に分かれ、プラチナライター、ゴールドライター、レギュラーライターを選ぶことができます。希望の予算や記事の品質に応じた記事外注ができることが魅力です。(※3000文字以上はゴールド、プラチナ、5000文字以上プラチナのみ選択可能)
- クラウドソーシングなのにライター選びの手間がない
- クラウドソーシングなのにコピー&目視チェックあり
- 予算に合わせて3種類のライターが選べる
| 運営企業 | 株式会社ウィルゲート |
| サービスプラン、料金目安 | ・オンライン発注プラン レギュラー:0.75円〜/文字 ゴールド:1.5円〜/文字 プラチナ:3.0円〜/文字 ※最小発注数:記事1本から ・オーダーメイドプラン レギュラー:1.2円〜/文字 ゴールド:2.3円〜/文字 プラチナ:4.5円〜/文字 ※最小発注数:最低30万円以上から |
| 備考 | プラチナライターのみ修正依頼可能。レギュラー、ゴールドライターには、発注記事数の30%まで非承認することが可能。 |
| お問い合わせ | https://works.sagooo.com/online_order |
クラウドワークス│株式会社クラウドワークス
取り扱い案件数で日本一を誇るクラウドソーシングサービスがクラウドワークスです。多種多様なライターが登録しており、未経験からフリーで生計を立てている方まで様々な方が登録しています。サテライトサイト用記事や、アフィリエイト用記事の外注化で使用されるケースが多いです。
ライターに執筆を依頼するには、クラウドワークス内で検索して見つけたライターに直接依頼する方法と、募集をかけてライターを集める方法があります。サグーワークスと比較すると、単価の交渉や作業範囲などライターそれぞれと行うことができる自由さがあります。自由な分、ディレクション作業の工数はかかるとも言えます。
仕事の依頼方法には、集めた応募者の中から選んだ人と仕事をするプロジェクト式や、募集時に制作物を提案してもらうコンペ式、応募者の選定はせず指定の業務を行ってもらうタスク式の3種類あります。記事外注では、主にプロジェクト式を利用して固定報酬や時間単価で契約すると良いでしょう。
- 日本最大級のクラウドソーシングサービス
- 多様なライターが登録している
- 多数のライターを募集できる
| 運営企業 | 株式会社クラウドワークス |
| 発注相場 | ・2,000文字の記事: 2,000円〜/記事、納期5日前後 ・インタビュー、取材:15,000円〜/記事(交通費別)、納期15日前後 ・SEOコンサルティング:50,000円〜 |
| お問い合わせ | https://crowdworks.jp/ |
記事外注で失敗しないための依頼のコツ
外注先の目星がついたら、あとは求める記事を作ってもらうのみです。しかし、丸投げすれば良い記事が自動的に納品されるともいきません。記事外注で失敗しないように、以下の依頼のコツを押さえておきましょう。
テストライティング、または少ない本数で依頼する
サービス内容が魅力的で、担当者が信頼できそうだとしても、あがってきた原稿の質が悪ければ記事外注の目的は達成できません。そこで、テストライティングや、トライアルで少ない本数での執筆を依頼しましょう。
記事作成会社としても、お客様の好みを把握するためのすり合わせの時間が必要なため、いきなり大量に発注いただくよりも、少ない本数から制作をご一緒できる方が望ましいことが多いです。また、可能であれば、すべて同じライターではなく、複数のライターに執筆してもらえないか相談してみましょう。複数のライターの記事を見ることで、クオリティを判断しやすくなります。
記事のレギュレーションを用意する
レギュレーションとは記事のルールです。どんなトンマナがいいのか、避けてほしい表現、言葉はあるか、どんな文章が好みか、漢字はひらくのかとじるのか、など細かに規定します。
レギュレーションを用意することで、記事ができあがってからの修正のやり取りが大幅に減ります。記事外注にあたって、避けられる手間は事前に避けられるよう準備しましょう。
記事で伝えたいことを明確に伝える
SEOコンテンツの制作となると、検索キーワードで上位表示することに重きを起きがちで、内容面での要求が漏れがちです。検索ユーザーに対して、どんなことを伝えて、どんなことを感じてもらいたいのか、自社サービスを記事内でこんな風に訴求してほしいなどといったことは、執筆前に外注先と調整しておくと良いでしょう。
文章構成を制作してくれる会社の場合は、そういったことが事前に確認できるため、イメージした納品記事があがってくるでしょう。
五月雨式に納品してもらう
記事の納品タイミングを一度にまとめてではなく、できた記事から順次納品してもらえないか相談してみましょう。五月雨式に納品してもらうことで、記事のフィードバックを早めにすることができ、あとから納品される記事にフィードバック内容を反映してもらうことができます。
さいごに〜信頼できるパートナーを選ぼう〜
記事外注サービスは数多く存在しますが、すべてのサービスが満足いくものとはいえないのが現状です。当記事で紹介した外注の準備や、外注先の選定方法、おすすめの外注サービスを参考に、安心して記事外注できるパートナーを見つけることができるよう願っています。
- Webライターになるには?記事作成会社の明かす失敗しない始め方 - 2023年8月22日
- 【8パターン】冗長表現とは?という・ことを省いて読みやすさを追求しよう - 2023年7月7日